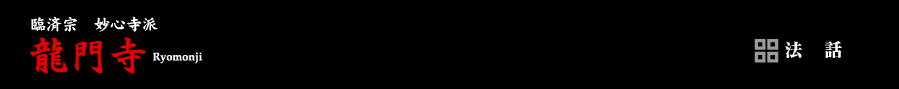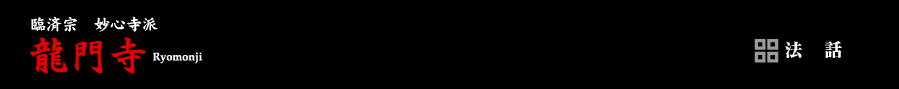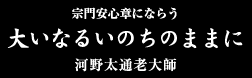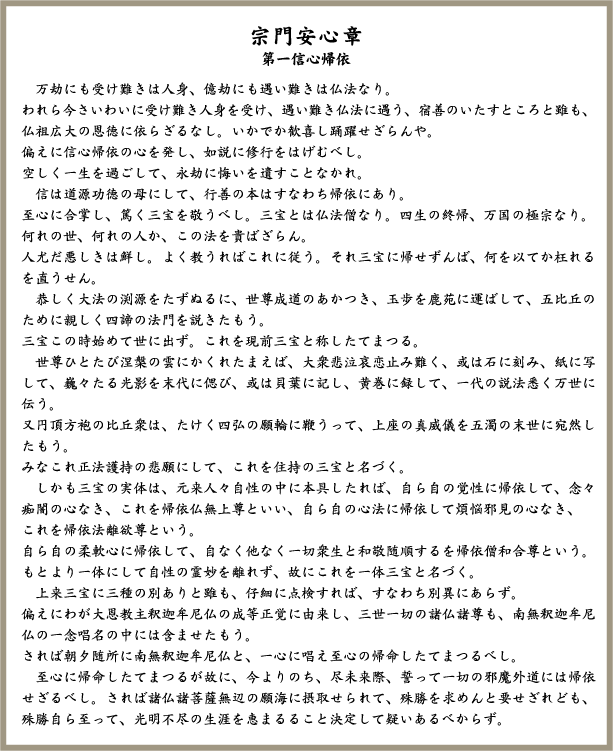【信心帰依の心】 信(まこと)の心に生きる
偏えに信心帰依の心を発し、如説に修行をはげむべし
ままならぬ心の故に
自分の心のあり方如何によって、ものごとや、人や、世のすがたが、すっかり変わって見えてきます。
この心こそ自己自身でありますが、ままならぬのがこの心であります。
釈尊はこの反省を、「法句経」の中で悲哀の情をもって語られています。
「心は独り動き、形体なく、胸の奥の洞窟にひそんでいる。捉え難く、軽々とざわめき、欲するままにおもむ
く」 と。
そして更に、「憎む人が憎む人に対し、怨む人が怨む人にたいして、どのようなことをしようとも邪なことを
めざしている心はそれよりもひどいことをする」 と。
人類最古の文明の一つが生まれた土地、メサポタミアの人びとが、粘土で作った書板に楔形文字で残
した詩があります。
きのう生まれたものが、きょうは死ぬ
つかの間のうちに、人間は闇に投げ込まれ
突然押しつぶされてしまう
喜びに歌を口ずさむときはあっても
たちまち嘆き悲しむことになるなる
朝と夜とのあいだに、人びとの気分は変わる
ひもじいときには亡骸のようになり
満腹になると、神とも張り合い
ものごとが順調にいってるときは
天にも昇るなどとしゃべるくせに
困ったときは地獄にも落ちそうだとわめく
このメソポタミアの詩人は、自分たちの心のありさまを反省をこめて素直にうたったのですが、およそ5千
年前のこの時代も、それから二千五百年後釈尊の時代も、そして今日も、なんと人間の心の基本的ありよ
うは少しも変わっていないことを思い知らされます。
苦悩こそ、解脱を欲する心こそ、仏心
しかし、正しくみちびかれるならば、心ほどたよりになるものはありません。
同じ「法句経」の中で「母も父も、そのほか親族がしてくれるよりも、さらに優れたことを、正しく向けられた
心がしてくれる」とあります。
釈尊は最晩年、なおも最後の旅をつづけながら、「アーナンダよ、わたしは疲れた背がいたむ」と
たびたびもらされるようになったと伝えられます。
喜んでいるかと思えば、たちまち嘆き悲しむ、正直というか、移り気というか、千変万化して止まないのが、
わが心でありますが、また困惑したときにその解脱の方法を、一番親身になって思ってくれるのもわが心で
あります。このだれもが等しく持って、ひと時も離れたことのない心の真実の道理を見すえ、そこに人の拠り
所を見たのが釈尊でした。
明治以降、先達のご苦労によって、われわれは、より多くの原始経典に接することが可能になりました。
そこで感じますことは、釈尊はじつによく、人の心の機微に通暁されていたということです。
釈尊がお示しになった法の一つは、いささかの妥協もない、因果律でしたが、それにあたたかい血を通わ
せて、かっての御自分の姿をわれわれの苦悩の中に見ているが如くに説かれているのに心打たれます。
釈尊は、単に因果の道理を説いたのではなく、因果の道理にかなった人間の心と身のありようを説かれた
のだと思います。「仏心とは、大慈悲心 是なり」のご生涯でした。
われわれは迷い、そして苦しみます。そしてその苦悩から脱れ、解脱することを望みます。自分も他人も
仏心のままにおれないことが、つらくて悲しいのです。それならば、ほかならぬその苦悩こそが、解脱を欲
する心こそが、仏心であり、仏心が本来そなえられている証ではありませんか。仏心が働くからこそ苦しくも
つらいのです。
この仏心は万人に具えられていて、かって失われたことのないものであることの道理を深く心にうなずいて
いくことを信心帰依(しんじんきえ)と申すのであります。そして「松のことは松に習え、竹のことは竹に習え」
であります。これは俳諧の道の革命を唱えた芭蕉の言葉でありますが、人間のことは人間のすぐれた先達に
学ばなければなりません。仏祖の説かれるが如く、この身心をみきわめ働かせることによって、この自己も世
界も限りなく高められてゆくはずであります。
信心不二、いま起こしている念いこそが仏心である
貪欲は人を害し憎悪をもたらす
1940年(昭和15年)、わが国が太平洋戦争に突入する前年、喜劇王チャーリー・チャップリンは、みず
から監督し、二役を演じて、映画「独裁者」を製作しました。
ユダヤ人強制収用所を脱走したチャップリン演ずる床屋は、独裁者ヒンケル総統に似ているのを幸いに総
統に変装して難を逃れます。ところが、うまく総統にまちがえられた床屋は、数万の兵士と群衆の前で、スピ
ーチしなければならない羽目になってしまいます。床屋はおろおろしながら、細ぼそと、それでも自分の思
いのありったけを語り始めると、いつしか熱がこもり、自分でも驚くほどの名演説になってしまいました。そして
拍手と大歓声につつまれたのでした。
「・・・私たちは他人の幸福によって生きることを願っています。断じて他人の苦しみよってではありません。
憎しみあい、軽蔑しあうのは真っ平です。この世界には全人類を養うだけの富はあるのです。貪欲が人類を
毒し、憎悪をもたらし、悲劇と流血を招きました。・・・知識を得て人類は懐疑的になりました。思想だけがあ
って感情が無く、人間性が失われました。知識より思いやりが必要です。思いやりがないと暴力だけが残り
ます。
・・・人びとよ、失望してはならない。貪欲はやがて姿を消し恐怖もやがて消え去り、独裁者は死に絶える。
大衆は再び権力を取り戻し、自由は決して失われないのです。兵士諸君、独裁者の奴隷になるな!・・・・
あなた方は、人生を自由にし、美しく素晴らしいものにする力を持っているのです。その力を駆使し、貪欲と
憎悪を追放しよう!文化の進歩が全人類を幸福に導くように。・・・・・・」
演説する独裁者ヒンケル、実は床屋に、私はチャップリンの真顔を見ました。
大歓声が静まると、いままでの熱弁とは打って変わった穏やかな口調で、はるかな空の雲に向かって「ハ
ンナ、聞こえるかい、元気をお出し」とユダヤ人狩りを逃れて何処にいるかわからない失意の恋人に呼びか
けるのです。ハンナとはまた、チャップリンの実母の名前でもありました。
「預言者、故郷にいられず」と言いますが、痛烈に風刺したナチス・ドイツのヒトラーのその後の狂気と、
50年後の現代社会をのありようを的確に予言していたチャップリンは、やがてアカ呼ばわりされてアメリカか
らも締め出されてしまいました。
アメリカがアカデミー賞を用意して、温かくチャップリンを迎えなおすまでの20年間、スイスのレマン湖畔
で、失意の日々を送るチャップリンの心は、おのずと家庭へと向けられました。そして「この20年間、はじめ
て幸福というものを知った」と80歳をすぎてからレマン湖畔時代を述懐しています。
私の幸せが社会の幸せ、社会の不幸が私の不幸
幸福は誰もが等しく求めるものでありましょう。
時代におもねず、人に媚びず、社会を厳しく風刺し批判し、阿修羅の如く仕事に打ち込んで、人びとを楽し
ませた青年壮年期には、必ずしも心の平安は伴なわなかったというのでしょうか。
人はまた誰も迷い苦悩しない者はいません。その姿を他者から見れば、懸命な立派な生き方と映るかもし
れません。 いずれにしても、外境に執われて迷い、迷いからくる心の痛みに苦悩するその痛みを苦悩は、
実は、何ものにも執われる必要もない、やすらぎの境地へいざなう心の智慧に他なりません。
これを仏心というのでしょう。仏心はわれわれが本来あるべきの姿にいないと、それが自己であろうと他人で
あろうと同じく痛みを感じて苦渋するのです。
仏心がそのようなものであってみれば、それは、褒められても増やさず、謗られても減らず、万人に具えら
れていて、かって失ったことのないものであることは自明の理であります。そのように身にも心にもうなずける
ことを悟るというのでありましよう。
信心銘に[信心不二、不二信心]とうたわれるように、この迷う心が悟るのであり、それ以外に悟る心も悟り
の心もあるものではありません。大事なことは、いま起している念いが、ほかならぬ仏心であると気づくことで
す。どうしてもそうとは信じられない状態を心の病いといいます。
臨済禅師が「病、不自信のところにある」説かれるところです。 わが心は元来、仏祖の心と一つであった、
自他不二あったと明らめ、私の幸せが社会の幸せであり、 社会の不幸は私の不幸であると見て取る心を、
信心帰依のこころと申すのであります。
チャップリンが生きた今世紀は、科学技術の著しい発達により、人類最大の恩恵を享けています。 反面、
近代兵器による戦争、人間自体が生み出す公害をはじめ、いくたの不幸をももたらしています。チャップリン
の床屋が言うように「貪欲と憎悪を追放し、文化の進歩が人類を幸福に導く」のか、 われわれ一人ひとりの、
ありようにかかっていることを思うとき、信心帰依の心は、時代と場所を超えて万人が失ってなってはならぬ,
人間の宝のはずであります。
生きがいのある人生と?
空しく一生を過ごして、永劫に悔いを遺すことなかれ。
生きがいのある人生とは?
ただ生存しているだけでなく、充実した人生をおくりたいとは、誰しもが願うところであります。 ある若い知
人が、こんなことを聞かせてくれました。役所に勤めて十数年になるが、一応順調な日々でした。家庭でも、
同じ職場に働く妻と子供二人にかこまれて、ごく当たり前の暮らしが続いていました。
ところが最近、十年一日の如き生活に、ふと空しさを感じるようになりました。いったいこのままででよいのだ
ろうか。ただ働く機械のように黙々と、同じレールの上を進むだけで、生きている意義があるのだろうか。
彼は坐禅と合気道をはじめてみました。何かを自分の意思で行い、生きている存在感、充実感をえたかった
のです。
そんなある日、退庁したあと、合気道の道場に通い帰ってみますと、待ちくたびれた妻は、夕食の支度を
したまま横になって、寝息を立てていました。彼はその寝顔をしみじみと見ているうちに、新しい心のゆれを
感じてきたといいます。自分が不安であるように、この妻にも同じような満たされざるものがあるのではあるま
いか。そんなことを思うと、彼は凍りつくように唖然としたというのでありました。
現代の科学技術発達の恵沢は、つい先頃の時代の人々の思いも及ばないほどに、生活便利にしました。
そして、人びとの身を喜ばせ、耳を楽しませ、味覚を満足させるものがますます増加しています。誰がこの人
生を厭いましょうか。しかしながら、外にあるものに心を奪われ、今日のように高度化した管理社会にあっては
人間疎外の波は、あたかも自然の如く、誰しもの上にに押し寄せてまいり、あるとき、冷徹な得体の知れない
深淵に望むような、不安な思いをすることがあるものです。
古人は「百年三万六千日、胡蝶夢中に、空しく春を送る」と訓していますが、人間百歳を数える人が増え
てきた今日こそ、この戒めはまた新たな共感を懐かせます。
江戸時代、一時、妙心寺派の僧であった儒学者、山崎闇斎は、会津藩主保科正之に「人生で最大の楽し
みは何であるか」と問われて、「私には三つの大きな楽しみがあります。 第一には、天地の間に生きとし生
ける
ものの多い中で万物の霊長と称させられ、物の道理を知ることのできる人間に生まれたということが、最大の
楽しみであります。その次に、世の中には治乱がある。 然るに今、太平の世に生まれて、書を読み道を学ぶ
ことができるのはこれまた大いなる楽しみであります。第三には、今の諸侯方、大名達は、みな深宮の内に
育てられて世の困苦を知らず、いたづらに酒色に耽って、一生を乱費してしまう。その中で貧賤に生まれて、
辛酸をなめて、 道を習い徳を養うことができるのは、この上もない楽しみである」と答えたとことであります。
私一個の命は、多くのものの命
この返答には、人生の楽しみを外のもののみに追い求めている保科公を含めた人びとへの皮肉が込めら
れているように思いますが、人間に生まれて、平和な世で人としての辛酸を味わい、道を学び徳を養うことを、
人生の最大の楽しみとしているというのであります。 生きることのできる憂いを抱いておればこそ、人生を意
義あらしめるべく努めることを、人生最大の喜びとして喜べるのでありましよう。
日々欠かすことなく、労務を共にするご老体を見かねたお弟子たちが、作業道具を隠してしまうと「一日作
さざれば、一日食らわず」という金言を吐かれたのは百丈禅師でありました。
今日、飽食時代と言われるときに生きるわれわれは、一日作さずして、三日分も食らう無意義な徒食をし
てはいないでしょうか。
わが盤珪禅師は、晩年、三度の食事毎に、その分量に大変気づかわれたそうです。健康で長生きのため
の食生活が提唱される今日では、ごくあたりまえのことのようですが、みんなそんなに長生きしてして、なに
をしようというのでしょうか。
ある人が盤珪さんに問いました。
「そんなに食事の分量を気にされるということは、命に執着があるからではありませんか。日頃のお言葉には
そぐいませんが」
盤珪さんは、
「そうではない。わしは命を粗末にはできん。君子は一日生きれば、一日世に利あり、無駄には死ねん」
と言われました。
われわれの命は、水や空気によって、また多くの植物の命をいただいて保たれています。 なれば、私一
個の命は多くのものの命であります。世に利することもなく、この命を無駄に使うほど罪なことはありません。
再び遇うことのない日々を無意義に送るほど、惜しむべきことはありません。
自ら円満なる人格を自覚すること、すべての人に尊厳なる人格を目覚めさせてゆくこと、言葉をかえていえ
ば、自らも人も、仏になってゆくこと以上の人生の喜びはないといってよいでありましょう。
無我の心こそ人生を生きる道すじの根本
信は道源功徳の母にして、行善の本はすなわり帰依にあり
時々刻々と変わるわがこころが心一人の心
最近、知人からこんな話を聞かせてもらいました。長崎に住む知人の友人で、ガンで闘病中の女性のこと
でした。この方は、病弱で定職に就けない夫を抱え、娘の進学を夢みて長いこと保険会社の外交契約員と
して頑張ってきました。
要領のいい人ではないが、まじめで、他人のことでもほっておけない性格だから、知り合いの人達からの励
ましの声も多かった。しかし、三年前のある日、疲れ果てて、とうとう倒れてしまった。直ちに入院、そして手
術。本人も、うすうす症状にについては察知していたらしいのですが、幸い四ヶ月で退院。自宅での静養を
きつく言い渡されたいたものの、入院中に受けた人びとの親切へのお返しがしたくて、まだ十分に回復して
いない身体で職場に復帰した。
ところが、暫くの間には状況は変わっていた。折角、苦労してこしらえていた自分の顧客は、同僚の手に
移っていた。会社も思いがけず冷たかった。しかしそれでも何とか前に進まなければならない。疲れると、
時折、友人の家に立ち寄っては、一休みするのが一つの救いでもあったのであろう。
そんな様子をじっと見ていた友人は、ある時尋ねてみた。
「そんなにまで一途なあなたをささえているのは何か」と。
そのご婦人はしばらくして言った。
「人生は苦なのでしょう」と。
幼い時、母につれられてお寺詣りをした折、和尚さんから聞かされた言葉だという。聞いた時は分からな
かった。しばらくは、苦を数字の九だと思っていた。
やがて父が逝き、兄達は次々と戦場に消えてゆき、そして、長崎に原爆が落ちた。直接の被害を受けな
かったが、成長するにつれて、和尚さんの言葉が実感として聞えはじめるようになった。そう感じると、苦し
みが大したものでなくなって、苦しみから逃げずに生きてきたように思うという。
この頃また、病がぶりかえして再入院。ベットの上で静かに横たわっていると、いま迄気づかなかった自分
が少し見えてきたようなような気がする。痛いときは痛い、淋しいときは淋しい、嬉しいときは嬉しい。病気は
早くなおりたいし、お金も欲しいなあと素直に言えるようになった。
そしたら、まわりのものの一つ一つがいとおしく、とても身近に思える。そして不思議と心が落ち着く。これ
まで、やれるだけは精一杯やったつもりである。これでいいのだと思う。
そして、これからの残り少ない日々を大切に生きていこうと思う。病窓からは西の海を見はるかし、烏帽子
岳という美しい山が見える。
雲ごとに姿を変える烏帽子かな
晩涼の山に向いて手を合わす
こんな句を詠んだのだそうです。
無我の心に居ることこそ信の心
お釈迦さまは、諸行無常を説かれました。諸行が無常ということは、すべて無我ということです。
生まれてから滅するまで、不変の「我」というものはない。だから、時々刻々移り変ってゆく。それなのに変
わらないことを求めたり、変わらないと思い込んだりするから、われわれは苦しむのです。
変わらないのは、諸行が無常で、すべて(諸法)は無我だということだけです。
元来、無我であるから、私は、去年の私と今年の私はとは多少ちがいます。今朝と今夜ともちがう、正装し
ている私、作務着の私、病気のとき、暑いとき寒いとき、その時その時の縁によって、時々刻々に変化する
のです。窓越に見える烏帽子岳もそうだ。頂上に白い雲がポッカリと浮かんでいるとき、雨雲に覆われてい
るとき、かすみたなびく、朝日のとき、夕日のとき、その姿を変えて止まることはない。山も私も同じ無常無我
を生きている。自分が病床に横たわり、すなおに無我にかえってみると、まわりの一つ一つがいとおしく、心
が落ち着く。これを涅槃寂静というのでしょうか。泰然と無常を生きる烏帽子岳が、親わしく有難く拝めるので
す。
このご婦人は、格別に仏の教えを学んだわけでもありません。特別な修行を積んだわけでもありません。で
すから先のような仏法の道理を踏まえて、句を詠んだとは思えません。 ただ悲しいことだけれども、ガンと
いう病が縁になって、おのづからこのような智慧の心が蔵されているとです。
信とは、辞書をひもときますと、まこと、まかせるという意味とありますが、信とは、諸行は無常で、すべては
無我であるという心にいることで、これがわれわれの信(まこと)の心です。
諸行が無常で、すべては無我であるということ、誰が信ぜずにおられましょうや。無我であればこそ、われ
われは相手の立場に立ち、相手の心を理解し、相手と一つになることができる。無我はこの世界に現存す
るすべてのものの存在の理であり、人が生きる道すじにの根本であります。「信は道源」であります。
そして、山やすべてのものに手を合せ、尊重し感謝できる心が持てる。これ以上の功徳が外にありましょう
か。 まさに、信は功徳の母であります。もろもろの善行もまた、無我のままの心でなければ、善行とは申せ
ますまい。善行を実践する心得は、無我の心に替えることにあるといわなければなりますん。
|