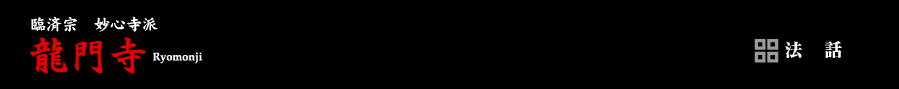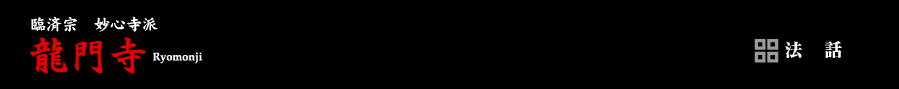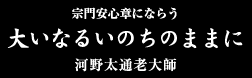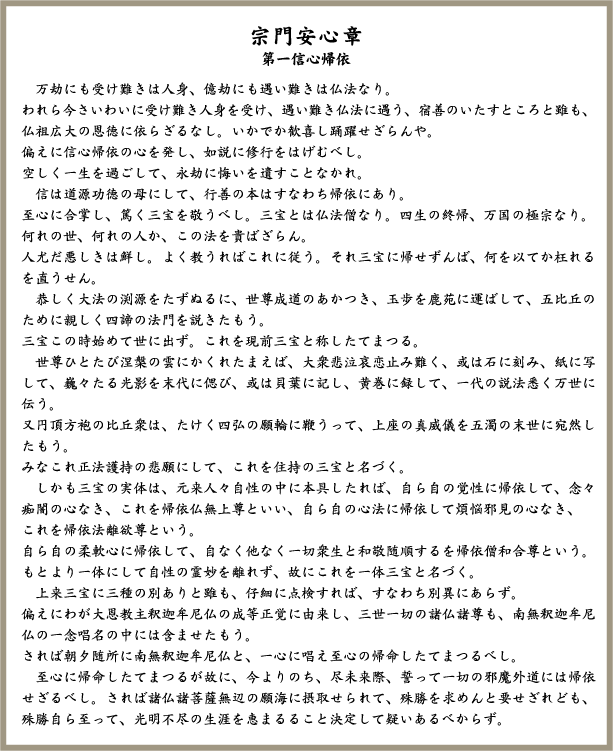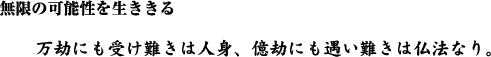今、生かされてあることの幸い
われら今受け難き人身を受け、逢い難き仏法に逢う。
宿善のいたすところと雖も、仏祖広大の恩徳に依らざるなし。
いかでか歓喜し踊躍せざらんや。
出会いはこの世の宝
よき人との出逢い、ことに人生の師と仰の邂ぐ人と逅は、人間にとってかけがいのない宝であります。
釈尊と同じ年に生まれたコーサラ国の王、パセナーディは、ある日釈尊にこのようなことを申しました。
「世尊よ、わたしのもとに、イシーダッタとプラーナという二人の工匠がいるのをご存知でしょうか。
彼らは、わたしの大工で、わたしは彼らに生業をあたえ、彼らはわたしによって名声を博した者です。
ところがある時のこと、わたしは軍旅にあって、彼らをともない、せまい家に宿ったことがあります。
その夜、彼らはおそくまで、世尊の説かれた法について語り合っていました。
さて、寝につくにあたっては、世尊のいますと聞く方向に頭をむけ、わたしの方に足をむけて寝たのです。
わたしは、もう、びっくりしするとともに、また、ほとほと感心したことであります。彼らのわたしにたいする尊敬は,世尊に対する尊敬の比ではないのです。これは、彼らが世尊の教えによってよほど素晴らしいものを与えられたからに相違ないと、思わざるをえません」(中阿含経) かく語った粗暴で聞こえる王自身もまた、釈尊に対して誰にもおとらぬ深い敬慕の念を抱いている人でした。
釈尊在世の時代も、人の一生が浮世という広漠たる大海の風波を渡ってゆくことに変わりはなかったはずです。それどころか、当時のインド社会は、個人の権利が平等に認められるような時代ではなく、不平等、不合理が渦巻く極端に階級差別のつよい社会でありました。階級制度を擁護するバラモン教の教説の下で、
人びとの心の奥には、この世は苦の世界あるというあきらめが社会通念としてありました。釈尊自身もまた,この世界は苦である言われたのですから。この苦なる世にすでに人と生まれ、ずでに四苦八苦の荒波を
まがりなりにも越えることができ、逢い難き釈尊のその人に遇い、人間平等、万物尊重の教えに、二人の工匠も、パセナーディ王もしたしむことができたのでした。
輪廻転生の悪循環からの今世での脱却の法
現代のわれわれは、釈尊の時代には想像もしなかったであろう受験戦争にはじまる競争社会の中で
人間のあくなき要求と無明が引き起こしている大気汚染、自然環境の破壊、薬物による人体の汚染、核問題、そして臓器移植に関わる脳死の問題等、あまたの社会問題をかかえる社会にいるにもかかわらず、
幸いにもいま生かされ、また遇い難き仏の教えに、釈尊滅後、二千五百年へだだったいま遇っています。
これは、偶然の事柄ではなく、まことに「宿善のいたすところと雖も、仏祖広大の恩徳」に依るものであると
いわなければなりません。
宿善とは、過去の世からの善き行為ということで、「宿善のいたすところ」とは、現在の自己の良きありよは、過去の良き行為の結果であるということです。だが、過去の原因による結果としての現在はまた、未来のありようを決する因であることは当然です。しかしこの因果、因縁の理の真実は、さほど単純に図式化できるものではありません。
釈尊在世当時のバラモン教をはじめとする多くの宗教は、前世の行為の果であると同時に、将来への因である現在を、宿命として今世では動かすことのできないものとしていました。そこで、今世はあきらめ、来世に希望を託して、今世では苦行を行じたり、施しなど善根を積んで功徳力を養い、その力によって、来世は苦のない安穏栄華の生にジャンプできるとしたのです。
釈尊はこのような考えに満足することはできませんでした。もし来世に苦のない生活が享受できたとしても、その享楽の果報によって、その次の世にはまた苦の生がある。 それならば、来世が如何ほど安穏であっても、それは真の安心とはいえません。このような迷いの輪廻転生は、そのこと自体が苦であって、これでは
まことに救われる時節はありません。
釈尊が求めた真実は、この輪廻転生の悪循環からの、今世での脱却の法であったのです。このことは仏教徒のふまえておかなければならない大切な事柄であります。
束の間の人生を賭けるよろこびとは?
なすべきことは、ただ、善行をなして功徳をつむ
久方ぶりに釈尊を訪問したコーサラ国のパセナーディ王は、釈尊に問われました。
「大王よ、どこに行っておられましたか」「世尊よ、王というものは、主権をにぎり、広い領土をかかえ、その保全の責任をもっているので、いろいろ王事があるものです。わたしは、ここのところ、それらの王事で忙しかっ
たのです」
釈尊はじっと王の顔を見ながら、「大王よ、では、こんな場合、どう思われるか。ここに信頼する者が一人、
家の方から馳せ帰ってきて「大王よ、いま、東のほうから、虚空のような大きな山が、すべての生きものを圧し
つぶしながら、こなたに進んでまいります。大王よ、いそぎ為すべきことなしたまえ」と申し上げたとする。
また、そのとき、西の方からも,北の方からも,南の方からも、同じく信任する家臣たちが馳せ帰ってきて、お
なじような注進があったとする。
大王よ、それは、恐ろしい事態であって、いうなれば、人類の破滅のときであります。王は、何のなすべきことがあると思われますか」「世尊よ、何のなすべきことがありましょうか。ただ、もう、生のあるあいだ、善行をなし、功徳をつむほかありますまい」
「大王よ、それは、たんなる喩えばなしではありません。わたしは、あえて、あなたに告げねばならない。
老いが王のうえにおしかかっている。死が王のうえにおしかかっいるのです」
「まことに、世尊よ、仰せのとおり、老いと死とは、おおいなる巌の山のように、私の一身に押しせまってきております。
なすべきことは、ただ,善行をなして、功徳をつむほかはなかったのでありました」
これは、[雑阿含教]に説かれるところですが、、今日も人びとは、生業には励み、暮らしをたて、その中でなにがしかの喜びと楽しみを求め、また得ているでありましょう。
しかし、日々の繁忙と、ひとときの享楽にかまかけて、真に気付かなければならぬことにうとく、なすべきことに愚かであるのが人の常であります。
無功徳の心でする行為こそ功徳である
中国、南北朝時代の梁の武帝は、みずから袈裟を着けて、仏典を講義する程の、文武両道にぬきんで板人でした。
それだけにダルマさんの渡来を知ると、礼を厚くして迎え、自信とともに誇らしげに尋ねました。
「私はいままで、多くの寺を建て、経典も出版し、貧者を救い、沢山の僧を養成してきました。どのような功徳がありましょうか」
ダルマさんが酬いたのは「無功徳ーなんの功徳もない」一句でした。これは、武帝にとって青天の霹靂でした。
仏法とは、世間にありながら、世間を超えた深い真実であります。
おかえしを求めてする善行は、慢心を積み重ねこそすれ、何の功徳にもなりますまい。何の功徳をも願求
するところの無い「無功徳」の心でする行為こそ、まことの功徳であったとうなずけなければなりません。
世間的価値は、世間を超えた仏法の自覚をまって、はじめて真に人びとに価値あるものになってゆきます。喜楽を求め、幸いを願うのが人情というものでありましょうが、確実に老い早晩死んでいく、そのわれわれが、束の間の人生を賭けて求めている幸いとは何なのでありましょう。
近年、わが国は経済大国として、世界から注目され、科学技術でも、世界をリードする国の一つになりました。
しかし、その繁栄とはうらはらに、他の非をあげつらうことには熱心で、己れ自身を見、自己を省みるということにはまことに希薄な悲しい風潮が、蔓延してきてはいないでしょうか。
このことは、来る二十一世紀が ゛こころの時代゛として問われねばならぬ所以であると同時に、仏教国といわれるわが国においても、一億総不遇仏法とでもいいましょうか、いかに仏法に遇うことが難事かの哀しい
証でもありましょう。
歌人、斉藤茂吉は、私淑していた師、伊藤左千夫が他界するや、うたいました。
あかあかと一本の道とほりたり たまきはる我が命なりけり
盲亀浮木の、この広大無辺な世界の中の、わが生死の日々で、人間が生きる上での、根源的価値として、生涯を託し切っていける教えに出逢い、波荒れる暗夜に航路を見失った船が、灯台の火を見出した如く、具体的実践の、あきらかな道に眼を開くことができた時、はじめて、その教え主と教法に逢遇した喜びと感謝が、おのずから湧き出てくるのではありますまいか。
そしてまた、人間として命を得たことに充足をおぼえるのであります。
いまの自分をどう生きるか
欲を去り執着を捨てて・・・
釈尊は、ご存知のように当時の伝統的苦行のあらゆる方法を、逐一実践すること六年に及びましたが、
現実の生老病死の苦悩を除く効果は得られず、身を苦しめることが、決して心の平安につながるものでないことをさとりました。しかし、もはや当時の修行方法で、頼るものはなかったのです。
このとき、古い仏典によれば、釈尊の心に一つのたとえが浮かんだとされています。ここに三本の丸太ん棒
がある。一本は水にぬれた生木であり、一本は水にぬれてはいないが、やはり生木であり、もう一本は乾燥した枯れ木である。どの丸太ん棒によく火を移すことができるか、というものです。
生木とは、貪欲と執着によって汚湿されている心であり、乾燥した枯木とは、欲や執着のないない心の状態
をたとえたものであります。いかほど熱心に努力修行に励んだとしても、その人の心が欲と執着からはなれていないならば、目的を達成することはできない。よしんばできたとしても、それは貪欲と執着の中のものに
他なりません。欲と執着をはなれた精神によってこそ、心の平安という目的は達せられるはずです。
釈尊は、ついに苦行を放棄して、現在ブッダガヤと称される地の、良く繁茂するヒッパラ樹の下に、吉祥草
をしいて座を作り、諸欲をはなれて安詳として坐禅に入られました。
ただ、「さとりを開かずんば、たとえ死してもこの坐をたたない」という一大決心のもとに。
坐すること七日、十二月八日の未明に至り、暁天にひときわ輝く金星の光が眼に入るや、忽然として悟りを開かれ、積年の疑念は一時に瓦解そ去ったのです。
思わず「奇なるかな、奇なるかな、一切衆生悉く如来の智慧徳相を具有す」と叫ばれ「草木国土悉皆成仏」なることを覚知されたことは、衆知のところであります。そしてそれは「わが心の解脱は不動なり。これわが
最後の(迷いの)生にして、もはや(迷いの)再生あることなし」と述懐される如く、確信に満ちた不動のものでありました。
しかし、この質的転換を果たした悟りの時の、釈尊の心理状況については、ほとんど経典は伝えていない
ようです。[雑阿含経]などで、「わが証徳せるこの法は、甚深にして難険、難解、寂静、美妙にして、尋思
の境を越え、至微にして、智者のみ能く知る所なり」と、釈尊みずから示されるだけです。姿、形のない悟りの心そのものを、言葉でまるまる示すことは不可能です。示してみても、それは相対的観念である説明にしかすぎません。だから、「尋思の境を超える」といって説かれなかったのです。
無我なる人間性の自覚
それを承知の上で臆せず、簡単に言ってしまいますなら、欲望や執着という一切の自我が、おのずから消滅していた釈尊は,計らずも、明星を見たとき、明星が自分でだったのです。明星と自分は不二のなるものだった。一切と不二である無我なる自己を直感てきに全身心に自覚されたのであります。この自他の区別も対立意識もない、無我なる純粋な人間性こそ、仏心にほかなりません。
無我なればこそ、因果律の世界にいて、因果に支配されず、生死の中にいて、生死も染めることはできないのであります。まさに輪廻苦からの脱却でありました。
この釈尊の悟りは、人類が発生以来、二、三百万年かけて、ようやくにしてたどりついた、人間尊厳の真実の法理の自覚でありました。
釈尊はこの悟りを十分に一人楽しまれた後、さらにその内容を反芻静慮されて、悟りの心からこの世界の
道理として説き出されたのが「因縁の法、縁起の法」と呼ばれるものです。
この世のすべては、無数の因と縁とのさまざまな関り合いによって存在するものであって、一切を創造する
絶対的な人格神のようなものがあるわけでもなく、常住不変の個体、たとえば霊魂のようなものは存在しない。すべては本来無我であって、何時生まれたことはないから、滅することもない。ただ因縁によって生滅の
相を取るにすぎぬということであります。因とは結果を生ぜしめる、内的直接原因となる自己の念いと行為のことであり、縁とは自己以外の間接原因で、社会や自然環境のありようです。これらが、互いに無数に関わって、いまのすべてであることは確実です。これを釈尊は「因縁」の一語によって、端的にとらえて示されたのです。肝心なことは、因縁の果として現成しているいまの自己をどう生きるかであります。
釈尊に霊魂が死後存在するかしないかという質問をした青年僧に、釈尊は毒矢の比喩もって答えられています。毒矢に当り苦しんでいる人が、矢を射た人物、家柄、名前、矢の種類、毒物が判明しなければ、矢を抜き去って治療しないとしたら、この人は死ぬであろう。大事なことは、いま解決不可能なことに固執して論ずることではなく、いまの自己の邪悪煩悩執着を除き、法にかなった道を歩くことではないか、と。
本来の自己は、父母の経験知識にすら汚されぬ無我の心であり「親の生みつけたもうたのは仏心のみ」
(盤珪禅師)であって、ましてや「親の因果」と明確に特定づけるようなもはないことを知らなければなりません。すべては、いまの自己のありように関わっています。
このように、いま遇い難き仏法に遇うことができているのは、過去の自己の善き行為の結果でありますが、
釈尊の懊悩求道による開悟がなければなかったことでありますし、その仏法を、今日まで伝えてきた祖師方
の求道と、為人済度の広大な慈悲に依るものと、言うほかはないのであります。
迷いの人間として生まれたからこその感激
諸行無常の嵐の中で・・・
わが南北朝時代、後醍醐天皇に仕え、楠木正成と並んで倒幕計画に主要な役割を果たして、南朝の二大
忠臣と称された藤原藤房卿は天皇を奉じて笠置にたてこもりましたが、ここも幕府に追われるところとなり
流浪の身となりました。
このとき帝の さしてゆく笠置の山を出しより 天が下にはかくれ家もなし という御詠をうけて たのむとて この下かげを宿とせば なお袖ぬらす松の下のつゆ と返歌されて、
天下広しといえども、一国の王にすら、静穏を得ることのできる寸土すらないことを、帝と共に嘆いたのでした。この歌はまた、たとえ平和な国土にいるとしても、自らが無事の人でなければ、平安な居拠はどこにもないことを暗示していたと、受け取ることができます。やがて、幸いにも建武政府の中興なりまして、後醍醐帝は迎えられて元首となり、藤原卿は、いま流に申せば恩賞局の筆頭にとなりました。
しかし、公家と武家との争いは絶えず帝の私的行賞が多く、まつりごとを顧みないのをいさめて官位を退いてしまいました。そして、行雲流水の身となって、行方をくらまし、遂には帰ることはなかったのです。
釈尊はあるとき、人生の姿を次のような比喩で,説かれています。
一人の旅人が、広い荒野で突然狂った象に出くわした。逃げ隠れする場所も無く、幸いにも古い井戸を見つけると、藤づるが下がっていた。それを伝って井戸の中に降りていくと、井戸の底には大蛇が口をあけて
待ちかまえているのが見えた。おどろいてあたりを見ると、そこにも四匹の大蛇がいて、旅人をねらっている
命と頼むのは一本の藤づるだ。その藤づるも、黒白のねずみが交代でその根をかじっているではないか。
もはや万事休す。生きた心地はない。
そのときふと顔をあげると蜂の巣から甘い蜜がぽたりと旅人の口へ滴り落ちてきた。旅人はもはや目前の
危険を忘れて、蜜を貪り求めているのである。ロシアの文豪トルストイも感激したという「白黒二鼠」のたとえです。 広野の旅人とは、われわれ自身に他ならず、追ってくる狂象とは、流れる時間であり、諸行無常の風でありましょう。古井戸とは、生死の深淵で、その底にうごめく大蛇は死の影であり、四匹の毒蛇は、欲の
ことであるわれわれの肉体に起る生老病死の四苦でありましょう。そして、藤づるとは、われわれの生命であり、黒白のねずみとは、夜と昼であり、したたり落ちてくる蜜とは官能的快楽であるとうなずけます。まこと
このたくみな説示を味わいますなら、誰しも無常の想いを深くし、求道の旅を志すにはおれないのではありますまいか。
生まれながらに具えられている仏心に目覚める
政権の中枢にいた藤房卿も人の世の無常を感じ、権力闘争ではかち得ない人間の真実を求めて、求道の
旅人となったにちがいありません。大灯国師の法嗣関山国師が、妙心寺の開山として任せられるや、その
膝下に身をゆだねたと伝えます。そして、国師が与えた「本有円成仏、なんとしてか迷倒の衆生となる」と
いう話頭に参じました。
「生まれながらに円満な仏であるはずの人間が、なぜか凡夫となって迷うのか」彫心鏤骨すること幾星霜、
時節到来し、みずから期するところあって、その心境を
比の心一たび了じて曾って失せず
人天を利益す 尽未来
仏祖の深恩 報謝し難し
何ぞ、馬腹と驢胎とに居せん
とうたい、その感激を吐露いたしました。生まれながらに具えられていた仏心に目覚めてみると、それは、
自分がかって迷っているときも、しばしも失ったことはなかったのである。そのことを肯心会得できたのです。
この円満なる人間性の本質こそは、人類を永遠に利益しづけるかけがいのないものである。この自覚を、
この歓喜を与えてくださった釈尊と祖師深恩には、いかほど感謝しても届かない、どんなに報いても足りるものではない。どうして馬や驢馬の腹の中に居るような、仏心にも目覚めず、無為徒食しておれようかと、全身
にみなぎる感激をうたっています。
迷いの人間と生まれたからこそ、この感激があった。いまは迷倒の衆生であることすら喜びであるといわんばかりの風情であります。狂象も毒蛇もも顔出しできぬ歓喜踊躍ぶりです。
人間社会には、もろもろの問題が現前いたします。釈尊だったら、祖師だったらどう対処されるであろうかと
心をくだく。それが広大な仏祖の恩徳に報いる道ではありますまいか。そのために、また仏祖の心を、行履
を限りなく学んでいかなければならないわけです。そして、現実と仏法とのかかわりを課題としていく、その
一コマ一コマに、無常の風に、別調に吹かれる人間としての喜びがあるのではありますまいか。
こう決してみれば、仏心本具の、ほかならぬこの凡夫に生まれえたことが、かえってかけがえのない喜びではありませんか。
この藤房卿こそ関山国師の法を嗣ぎ、妙心寺第二世となった授翁宗弼禅師です。今日、他国に誇れる
われわれの日本の伝統文化のほとんどは、この法流に養われ、培われて今日に至っているのであります。
|